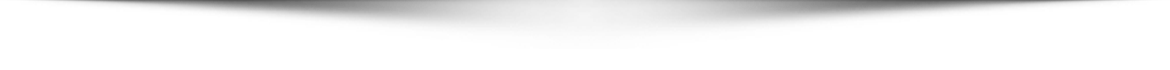シンプルなオペアンプ測定
オペアンプは、差動入力とシングルエンド出力を備えた非常に高利得アンプです。 高精度のアナログ回路で使用されることが多いため、その性能を正確に測定することが重要です。 しかし、開ループ測定では、107以上の高い開ループ利得が得られるため、ピックアップ、浮遊電流、またはゼーベック(熱電対)効果によるアンプ入力の非常に小さな電圧からの誤差を回避することが非常に困難になります。
サーボループを使用してアンプ入力にnullを強制することにより、測定プロセスを大幅に簡素化することができ、テスト対象のアンプは本質的に独自の誤差を測定することができます。 図1は、この原理を採用し、補助オペアンプを積分器として使用して、非常に高いdc開ループ利得で安定したループを確立する汎用回路を示しています。 スイッチは、以下の簡略化された図に記載されているさまざまなテストの性能を容易にします。

図1の回路は、測定誤差の大部分を最小限に抑え、多数のdcパラメータと少数のacパラメータの正確な測定を可能にします。 追加の”補助”オペアンプは、測定されるオペアンプよりも優れた性能を必要としません。 被試験デバイス(DUT)のオフセットが数mVを超える可能性がある場合は、補助オペアンプを±15V電源で動作させる必要があります(DUTの入力オフセットが10mVを超える可能性がある場合は、99.9k ω抵抗R3を小さくする必要があります)。
DUTの電源電圧+Vと–Vは、同じ大きさで反対の符号です。 システムのグランドリファレンスは電源の中点であるため、この回路を使用した”単電源”オペアンプでも対称電源が使用されます。
補助アンプは、積分器として、dcで開ループ(フルゲイン)になるように構成されていますが、その入力抵抗と帰還コンデンサは帯域幅を数Hzに制限します。 これは、dutの出力のdc電圧が補助アンプのフルゲインによって増幅され、1000:1の減衰器を介してDUTの非反転入力に印加されることを意味します。 負帰還は、DUTの出力をグランド電位に強制します。 (実際には、実際の電圧は補助アンプのオフセット電圧です—または、本当に細心の注意を払うならば、このオフセットに補助アンプのバイアス電流による100k Ω抵抗の電圧降下を加えたものです-しかし、これはグランドに十分に近く、特に測定中のこのポイントの電圧の変化が数マイクロボルトを超える可能性は低いため、重要ではありません)。
テスト-ポイントTP1の電圧は、DUTの入力に印加される補正電圧(誤差に等しい大きさ)の1000倍です。 これは数十mV以上になるため、測定が非常に簡単です。
理想的なオペアンプにはゼロオフセット電圧(Vos)があります。 実際には、オペアンプのオフセットは数マイクロボルトから数ミリボルトの範囲であるため、出力を中間電位にするには、この範囲の電圧を入力に印加しなければなりません。
図2は、最も基本的なテストオフセット測定の構成を示しています。 TP1の電圧がオフセットの1000倍のとき、dut出力電圧はグラウンドにあります。

理想的なオペアンプは無限の入力インピーダンスを持ち、入力に電流は流れません。 実際には、小さな”バイアス”電流が反転入力と非反転入力(それぞれIb–とIb+)に流れます。 それらは、オペアンプの種類に応じて、数フェムトアンペア(1fA=10—15A—数マイクロ秒ごとに一電子)から数ナノアンペアまで、あるいは非常に高速なオペアンプでは一つまたは二つのマイクロアンペアまでの範囲であることができる。 図3は、これらの電流の測定方法を示しています。

この回路は図2のオフセット回路と同じで、2つの抵抗R6とR7をDUT入力と直列に追加しています。 これらの抵抗は、スイッチS1とS2によって短絡することができます。 両方のスイッチを閉じた状態では、回路は図2と同じです。 S1がオープンのとき、反転入力からのバイアス電流はRsに流れ、電圧差がオフセットに加算されます。 TP1(=1000Ib–×Rs)での電圧変化を測定することにより、Ib–を計算することができ、同様に、S1を閉じてS2を開くことにより、Ib+を測定することができます。 電圧がTP1で測定され、S1とS2の両方が閉じ、その後両方が開いた場合、Ib+とIb–の差である”入力オフセット電流”Iosが変化によって測定されます。 使用されるR6とR7の値は、測定される電流に依存します。
5pA以下のIbの値については、大きな抵抗が含まれているため、この回路を使用することは非常に困難になります。
S1とS2が閉じている場合、Iosは100Ωの抵抗に流れ込み、Vosに誤差が発生しますが、Iosが測定されたVosの1%を超える誤差を生じるのに十分な大きさでない限り、この計算では通常無視されることがあります。
オペアンプの開ループdcゲインは非常に高くなる可能性があります; 107を超えるゲインは不明ではありませんが、250,000と2,000,000の間の値がより一般的です。 Dcゲインは、Dut出力と1-Vリファレンスの間でR5をS6でスイッチングすることにより、DUTの出力を既知の量(図4では1Vですが、デバイスがこれ R5が+1Vの場合、補助アンプの入力がゼロ付近で変化しないようにするには、DUT出力を-1Vに移動する必要があります。

TP1での電圧変化は、1000:1減衰し、DUTへの入力であり、出力の1-V変化を引き起こします。 このことからゲインを計算するのは簡単です(=1000×1V/TP1)。
開ループacゲインを測定するには、DUT入力に所望の周波数の小さなac信号を注入し、その出力で得られた信号を測定する必要があります(図5のTP2)。 これが行われている間、補助アンプはDUT出力で平均dcレベルを安定させ続けます。

図5では、ac信号は10,000:1減衰器を介してDUT入力に印加されます。 この大きな値は、開ループ利得がdc値の近くにある可能性がある低周波測定に必要です。 (たとえば、ゲインが1,000,000の周波数では、1V rms信号がアンプ入力に100μ Vを印加し、100V rms出力を供給しようとするとアンプが飽和します)。 したがって、ac測定は通常、開ループ利得が1に低下した周波数までの数百Hzから数百Hzの周波数で行われます-または低周波ゲインデータが必要な場合は、低入力振幅で非常に慎重に行われます。 示されている単純な減衰器は、浮遊容量に細心の注意を払っても、最大100kHz程度の周波数でのみ動作します。
オペアンプのコモンモード除去比(CMRR)は、コモンモード電圧の変化に起因する見かけのオフセット変化とコモンモード電圧の印加変化との比です。 多くの場合、dcでは80dB~120dB程度ですが、より高い周波数ではより低くなります。
テスト回路はCMRRの測定に理想的です(図6)。 同相モード電圧はDUT入力端子には印加されず、低レベルの影響で測定が中断される可能性がありますが、電源電圧は変更されます(同じように、つまり、 回路の残りの部分は邪魔されずに残されます。

図6の回路では、オフセットはTP1で測定され、電源は±V(この例では+2.5Vと-2.5V)で、両方の電源は+1Vから+3.5Vと-1.5Vまで上昇します。 オフセットの変化は1Vのコモンモードの変化に対応するため、dc CMRRはオフセットの変化と1Vの比です。
CMRRは、コモンモードの変更に対するオフセットの変更を指し、総電源電圧は変更されません。 一方、電源除去比(PSRR)は、総電源電圧の変化に対するオフセットの変化の比であり、同相モード電圧は電源の中間点で変化しません(図7)。

使用される回路はまったく同じですが、違いは、総電源電圧が変更され、共通レベルは変更されないことです。 ここでスイッチは+2からです。5Vおよび-2.5Vから+3Vおよび-3V、合計電源電圧が5Vから6Vに変化します。 計算も同じです(1000×TP1/1V)。
ac CMRRとPSRRを測定するには、図8と図9に示すように、電源電圧を電圧で変調します。 DUTはdcで開ループ動作を継続しますが、ac負帰還によって正確なゲインが定義されます(図では×100)。

ac CMRRを測定するために、DUTへの正電源と負電源を振幅が1-Vピークのac電圧で変調します。 両方の電源の変調は同じ位相であるため、実際の電源電圧は定常dcですが、同相モード電圧は2V p-pの正弦波であり、DUT出力にはTP2で測定されるac電
TP2のac電圧の振幅がxボルトピーク(2xボルトピーク対ピーク)の場合、DUT入力を基準とするCMRR(つまり、×100acゲインの前)はx/100Vであり、CMRRはこれと1Vピーク比である。

AC PSRRは、正電源と負電源のacを位相が180°ずれた状態で測定します。 これにより、電源電圧の振幅が変調され(この例では1Vピーク、2V p-p)、同相モード電圧はdcで安定したままになります。 計算は前のものと非常によく似ています。
結論
もちろん、測定する必要があるかもしれないオペアンプのパラメータや、他にもいくつかの測定方法がありますが、最も基本的なdcとacパラメータは、簡単に構築され、容易に理解され、問題から著しく解放された単純な基本回路で確実に測定することができます。
2018年1月:C1=1uFをC1=5uFに変更しました。 補助オペアンプ積分器は、最大10dbまたは約40hzで閉じたループピークを引き起こし、40hz発振に変わるのに十分な利得を持っていることが判明しました。
シミュレーションでは、極周波数を5倍減少させることで防止できることが示されています。